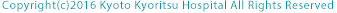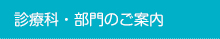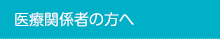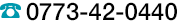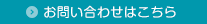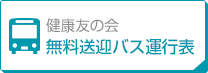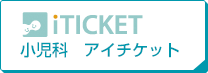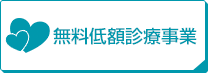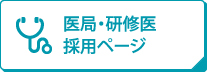採用情報
- 京都協立病院トップページ
- > 採用情報
研修医・医学生
初期研修要項
1. 京都協立病院の特色
- 人口約3万人(2023年5月現在)の綾部市と人口約7万5千人(2023年5月)の福知山市の境界に位置する地域基幹病院のひとつ
- 診療科:一般内科、一般外科、小児科(外来のみ)、皮膚科(外来のみ)
- 99床(地域包括ケア病床52床、回復期リハビリテーション病床47床)
- 1983年開設以来積み上げてきた歴史と実績
- 地域の幅広いニードに答えるために2004年に高津に現京都協立病院を新築移転。
今までの救急を含む急性期病院機能から介護保険療養病床、および医療保険療養病床を兼ね備えたケアミックス型病院として新たに生まれ変わる。 - 京都北部地域に4つの関連診療所および4つの在宅介護ステーションをもち、在宅医療を支援
- 「健康友の会」と協同した双方向性の地域医療の実践を重視
2. 当院で特に目指す医師像
- 地域に愛情を持ち、住民の心のわかる心優しい医師
- 病状的に社会的に困難なケースでも最後まで診きる責任感のある医師
- プライマリケアに要求される救急対応を含めた急性期疾患および高齢者の多様な問題に対応できる能力を身につけた頼りになる医師
3. 研修期間と定員
- 厚労労働省の地域医療研修カリキュラムに則り2年次のうちの6ヶ月(うち1ヶ月は診療所研修)
- 同一期間の定員は2名まで
4. 一般目標
- 地域住民の安心と健康作りに貢献する
- チーム医療の一員として協調性を発揮できる
- 救急対応を含めた急性期疾患および高齢者の多様な問題に対する内科的標準診療能力を身につける
5.獲得目標
【基本的能力】
- 多様なセッティング(医師同士で行う症例ディスカッションや看護師との情報共有カンファレンスなど)に応じた適切な症例プレゼンテーションができる
- POSに基づいた疾患アプローチ、カルテ記載ができる
- レントゲン、CTなどの読影、心電図や血液ガス分析、血液検査結果などの解釈により適切に患者の状態を評価し、治療または意思決定に活用できる
- 基本的診断的検査や基本的治療手技ができる
- 医療保険制度の大枠を理解する
【患者ケア】
- 特に高齢者の多様な疾患/病態に対し、適切な診断、治療能力を身につける
- 「急性上気道炎」をはじめとしたcommonな疾患から2次救急疾患までの1次対応ができる
- 限られた条件で行う在宅医療の限界を知り、病棟医療との違いを認識する
- 患者会での講演などに積極的に参加し、地域の健康づくりに貢献する
【特殊技術】
- 腹部エコーによる臓器スクリーニングができる
【対人間コミュニケーション】
- 患者やその家族の気持ちに配慮しつつ適切なインフォームドコンセントを行い、意思決定のプロセスを共有できる
- 患者家族や他の医療機関とのコミュニケーションを大切にしつつ入院から退院までを円滑に運ぶ能力を身につける
- スタッフや医師と適切にコミュニケーションをとり、患者ケアに活かすことが出来る
【プロフェッショナリズム】
- スタッフの質の向上のために積極的に学習会を設けて教える
- 多様な価値観を尊重しつつ、患者様の利益を優先した医療を提供できる
- チーム医療の一員であることを自覚し、医療スタッフと協調して楽しく仕事をすることができる
【その他】
- 学会発表を1回は行う
- 剖検症例1例以上をめざす
6.方略
【指導方針について】
外来:指導医によるプリセプティング
病棟:直接指導医とのマンツーマン指導によるOn the job trainingを原則。手技でも直接監督下での実施を原則。
当直:指導医とのセット当直。はじめは2ndコール、技量に伴い1stコール。
往診:診療所師長同伴によるサポート、指導医による事後フィードバック
【特殊手技】
- 腹部エコー研修:1単位/週
【学術関係】
- 抄読会(1/2週)
- 家庭医療学コアレクチャー(1/月)
【診療の質を向上するための各カンファレンス】
- 内科カンファレンス(1/週)
- 指導医カンファレンス(1/週)
- 外来指導カンファレンス(1/週)
- 研修医病棟カンファレンス(1/週)
- 振り返り(デス) カンファレンス(1/月)
【その他】
- 医療懇談会、患者会等での講師
7.具体的スケジュール例
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 早朝 | 抄読会 | 病棟 | ||||
| AM | 病棟 | 病棟 | 病棟 | 外来 | 病棟 | |
| PM | 往診/ 医局会議 |
|||||
| 夜 | 内・外 カンファ |
8.評価
【形成的評価】
- ブロック研修委員会での360度評価(評価者:指導医、外来・病棟看護師/ケアワーカー、薬剤師、診療所看護師、事務)(毎月)
- ブロック研修委員会での自己振り返りによる自己評価(毎月)
- 自己評定評価(3ヶ月に1回)
- 指導医による直接観察とSEA(Significant Event Analysis )(随時)
- 県連研修管理委員会での評価(3ヶ月に1回)
【総括的評価】
- 院内症例検討会(6ヶ月に1回)
- 地協研修医症例検討会(1年に1回)
- 厚労省の総括的評価(1年に1回)
- 腹部エコー総括
【評価モジュール】
- 研修医A(前半6ヶ月)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形成的評価 | ブロック研修委員会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 自己評定評価 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 指導医直接観察とSEA | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 研修管理委員会(県連) | ◯ | ◯ | |||||
| 総括的評価 | 腹部エコー総括 | ◯ | |||||
| 地協研修医症例検討会 | |||||||
| 厚労省総括的評価 | |||||||
| 院内症例検討会 | ◯ |
- 研修医B(後半6ヶ月)
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形成的評価 | ブロック研修委員会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 自己評定評価 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 指導医直接観察とSEA | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 研修管理委員会(県連) | ◯ | ◯ | |||||
| 総括的評価 | 腹部エコー総括 | ◯ | |||||
| 地協研修医症例検討会 | ◯ | ||||||
| 厚労省総括的評価 | ◯ |
9.指導医
| 医師名 | 専門分野など | |
|---|---|---|
| 玉木千里 | 院長 |
・京都北部総合診療専門研修プログラム統括責任者 ・日本内科学会総合内科専門医・指導医 ・日本リハビリテーション医学会専門医 |
10.備考
日本内科学会の規定する教育病院(京都民医連中央病院)の連携病院という形で、当院での経験症例を内科学会認定試験の症例として運用することも可能